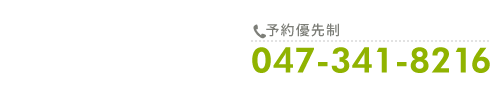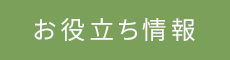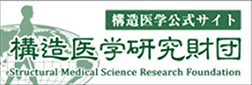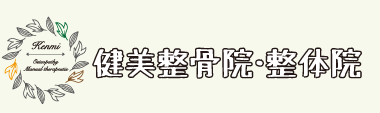はじめに
「食事のたびに顎に痛みが出る」「あくびをしたり笑ったりするとズキンと痛む」
「顎の痛みだけでなく頭痛やめまいも出てきた」
この顎の痛みはものすごいストレスがあります。
そう断言できる理由は私自身が「顎関節症」を体験しているからです。
私の場合は「空手の稽古による顔面部の打撃」により負傷したものですが苦笑
歯医者や整形外科に行ったけどなかなか改善しないあなたへ、千葉県松戸市の整体院が
「顎の痛みでお困りの方のお役に立てますように」との想いでブログを書いて行きます。
顎関節の解剖
顎関節とはどうなってるのか、解剖を説明していきます。
硬組織としては、下顎骨の下顎頭と頭蓋骨の下顎窩が、顎関節を構成しています。
人間に進化する過程で、下顎骨の厚みが薄くなってきたのも一因となっています。
それも含めて顎関節の安定性は非常に低く、だからこそ顎関節症でお困りの方が多いと言えます。
 次に軟部組織としては、画像のように関節円板・関節円板後部組織・外側翼突筋など、動かす筋肉は他に代表的な側頭筋や咬筋などの咀嚼筋が挙げられます。
次に軟部組織としては、画像のように関節円板・関節円板後部組織・外側翼突筋など、動かす筋肉は他に代表的な側頭筋や咬筋などの咀嚼筋が挙げられます。
顎関節症の5つの種類
「顎関節症」との文字通り、顎の関節や近くの筋肉の異常、痛みを総称して呼びます。
そして「日本顎関節学会」によると顎関節症の種類は5つに分類されるようです。
⑴顎関節症1型
咀嚼筋障害を主としたもの
⑵顎関節症2型
関節包・靭帯障害(円盤後部組織・関節包・靭帯の慢性外傷性病変を主としたもの)
⑶顎関節症3型
関節円板障害(関節円板の異常を主としたもの)
a:復位を伴う関節円板転位
b:復位をともなわない関節円板転位
⑷顎関節症4型
変形性関節症(退行性病変を主としたもの)
⑸顎関節症5型
上記の分類に該当しないもの
人間の身体における顎の働きとは
一番先に挙げられる、重要な働きとしては「ものを食べるときに咀嚼する」事でしょう。
それ以外は飲み込む時・言語発生・あくび・歯ぎしり・いびきなどでも動く、非常に運動する頻度の高い関節です。
しかし、人間は完全二足歩行で移動や直立の運動ができる事が知られています。
それを深く考えると、頭部(頭蓋骨)と組み合わさる下顎骨がそれぞれ平衡感覚(バランサー)
として、人間の身体に大きな役割を持っているのではと推測されます。
 それをわかりやすく証明してくれるのが、ウサインボルト選手。早かったですね。
それをわかりやすく証明してくれるのが、ウサインボルト選手。早かったですね。
画像をよく見ていただくとわかると思いますが、コーナを駆け抜けるのに身体は大きく傾いていますが、頭の軸と合わせて顎は直立に近づき、平衡性を保持しようとするのがわかります。
これは人間に限らず、四つ足動物や空を飛ぶ鳥やコウモリなどにも観察確認できる事であり、頭位軸平衡性と言います。そのバランスをとる頭蓋骨のすぐ下にブランコのように、存在する下顎骨。
これも顎関節を構成する中で、人間の大きなバランスに影響があることは想像しやすいでしょう。
また、競技の特性から「同じ方向に身体を傾けて走り滑る」スピードスケーターには共通した顎の偏位が確認できることも上記の裏付けと言えるでしょう。
顎と身体のバランスを知る実験
上記のように頭位軸が身体のバランスを大きく取っていること、それに付随する下顎骨も大きく
人間の身体のバランスに影響することを体感していただく、簡単な実験があります。
 腰掛け椅子に足の裏をしっかり床につけて、背筋を伸ばして「姿勢良く」座ってください。
腰掛け椅子に足の裏をしっかり床につけて、背筋を伸ばして「姿勢良く」座ってください。
その状態で上の歯と下の歯の奥歯をそっと噛み合わせて見てください。
普通に奥歯が噛み合うのがわかりますでしょうか。
 次に一番上の写真の「姿勢良く座る」状態から「少しおじぎをする」ような態勢を取ります。
次に一番上の写真の「姿勢良く座る」状態から「少しおじぎをする」ような態勢を取ります。
そして、先ほど同様に「奥歯を合わせるように歯をそっと近づける」と
どうでしょう、前歯が噛み合わさるのが体感できるでしょう。
 最後に一番はじめの「姿勢のいい座り方」から上半身を後ろに仰け反る座り方をしてください。
最後に一番はじめの「姿勢のいい座り方」から上半身を後ろに仰け反る座り方をしてください。
そして今まで同様に、奥歯を噛み合わせるように歯を近づけてください。
今度は奥歯でも前歯でもない「変なところ」というか、前歯と奥歯の中間あたりで歯が接触するのがわかるでしょう。
つまり、人間の身体の状態によって「歯の噛み合わせと顎の関節の動き」は大きく影響することが
言えるのです。
修学旅行の振替休日でたくさん寝た長男の寝起きに、写真モデルをお願いしました。
そんな事から、寝癖はご勘弁を。苦笑
顎関節症が整体で良くなる5つの理由
顎関節そのものを整復する処置を行う
顎の関節を知り尽くしているからこそ、顎の関節を正常に近づける「整復」する処置が出来ます。
指の中に収まるほど小さな関節ですから、解剖学だけでなく「なぜ顎の関節が正常に動かないのか」を見極めて、必要最小限の整復手技力を持って対応していきます。
顎関節と協調する頚椎を整復する処置を行う
口を開けるとき、閉めるときはそれぞれ顎の関節と強調して動く関節があります。
頚椎の第2・第3・第4頚椎の間に存在する関節です。
なぜ、顎と頚椎が協調して動くのかは解剖学的に説明していく事もできるのですが、簡単に説明すると、
❶顔を上に向けるようにすると(頚椎後屈)口が開けやすい(顎関節が動きやすい)
❷顔を下に向けると(頚椎前屈)口が開けにくい(顎関節が動きにくい)
❸首を左に傾けると(頚椎左側屈)右の顎関節が開口制限
以上の事から、顎の関節を整復するだけでなく、症状にもよりますが、強調して動く頚椎を整復しなければ、本来の顎関節の動きを改善することは出来ません。
写真は頚椎を整復する専用の治療器具での処置練習を行う、新人の成田先生です。
骨盤を整復する処置を行う
上記に挙げた頚椎は重要です。
しかし、その頚椎はすぐ下に胸椎、その下に腰椎と「脊椎(背骨)」として、土台となる骨盤につながっています。
顎関節症の症状にもよりますが(顎関節由来か骨盤を含めた体全体由来か)いくら顎関節を整えても、協調して動く頚椎を整えても、身体の土台の骨盤が傾いていれば、頚椎を含む背骨は捻れてきます。
顎関節の動きをよくする専用のテーピング処置を行う
顎の関節に貼るものではなく、決められた場所に貼付する事で顎の「ガクガク」するクリックの動きを正常に近づける「バリアM」という構造医学から作られている「顎関節専用テーピング」が存在します。
これを、同じ症状の顎関節症の患者さんに処置するかしないかでも、症状安定までに大きく差が出てくるのを当院では確認しています。
 顎の関節を空手の顔面の打撃で痛めて、整復した後に「バリアM」を貼ってる写真です。
顎の関節を空手の顔面の打撃で痛めて、整復した後に「バリアM」を貼ってる写真です。
透明なので、どこに貼ってあるかわかりませんよね。
上記の処置を含めて多くの顎関節の改善例があるから
2回の施術で顎の痛みが治まりました!
何年も前に、顎を開けると開けられないくらい強い痛みが出たことがありました。
今回も特に右あごが開けるときに「ガクガク」とスムーズに口を開けられないのと、強い痛みが
出て食事や口を開ける動作の全てで辛く、困っていました。
そこで思わず、スマホで「顎関節症・痛い」と検索したら近所で「健美整骨院・整体院」さんが
実績もおありだったので、お試しで顎関節整体を受けて見ました。
すると一回の施術で半分以下くらいに痛みも動きのよくなり、すごい嬉しかったです。
今は学生で、通いやすいように特別に学生料金で受付でくださったのもありがたかったです。
◆なぜ、他にも選択肢がある中で当院を選んだのですか?
検索したら健美さん以外で「顎関節症」を扱う整体院がなかったから。
HPに多くの症状で多くの口コミを目にしたから。
◆なぜ、「何もしない」という選択肢があったのに当院へ来院されましたか。
毎回、食事のたびに出る動きの悪さや痛みで正直「楽しく美味しい食事時間」
が憂うつに感じ始めていたからです。
松戸市20代ASさん
※効果には個人差があります。
【院長後期】
ASさん。貴重な顎関節症の喜びの声をくださり、ありがとうございます!
顎の痛みが早く取れて何より嬉しく思います。
ただ、説明させていただいた通り「繰り返し顎の痛みを出さない」
強い体になるまでには、まだ時間がかかります。
また「違和感・痛み」を感じる前に、早めに診させてください。
貴重な声を紹介させていただき、本当にありがとうございました。
千葉県松戸市の整体師が顎関節について解説しました。
顎でお困りの方はどうぞお気軽にご相談くださいませ。
TEL047ー341ー8216